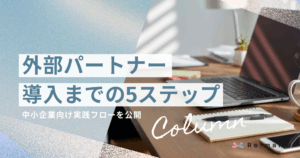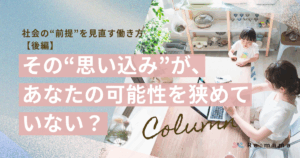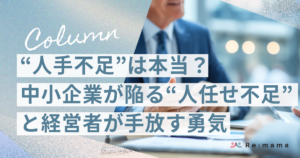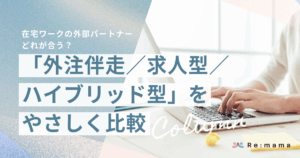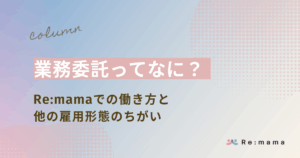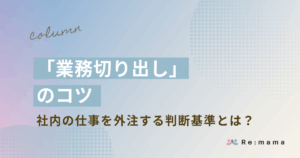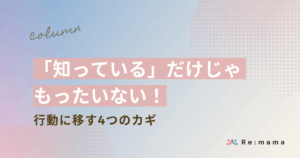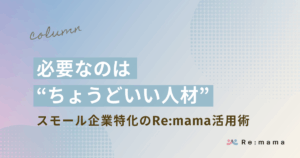出産や介護でキャリアが途切れる社会は、誰のせい?〜“働けない”のではなく、“働ける環境がない”だけ〜
私たちは、いつの間にか“決めつけられた前提”の中で働いているのかもしれません。
「ママだから、キャリアは一度止まるもの」
「家庭を優先したいなら、正社員は難しい」
「働けない」のではなく、「働ける環境が用意されていない」だけかもしれません。
本コラムでは、出産や介護などのライフイベントをきっかけに見えてくる“社会の構造”と“無意識の思い込み”という2つの壁に焦点を当て、Re:mama(リママ)が考える「選べる働き方」「自分らしいキャリアのつくり方」について前後編でお伝えします。
「辞めたくて辞めたわけじゃない」
Re:mamaに登録しているママたちから、よく聞く言葉があります。
「本当は仕事が好きだったんです。でも、出産のタイミングで部署がなくなってしまって…」
「介護と両立しようとしたら、“難しいんじゃない?”と言われて…」
“辞めたいから辞めた”わけではなく、辞めざるを得なかった。
そんな経験をした女性は、決して少なくありません。
それは個人の努力不足ではなく、社会の仕組みの問題。
誰もがライフイベントを迎えるのに、それを「キャリアの断絶」として扱う構造こそが、変わるべきなのだと思います。
出産や介護が“デメリット”にならない社会にしたい
私はかねてより、出産や介護などのライフイベントによって、これまで築いてきたキャリアが一度リセットされてしまうような社会のしくみに、違和感を持っていました。
「出産や介護がデメリットにならなければ、もっと活躍できる女性は多いはず」
そう感じたことが、Re:mamaを立ち上げた原点でもあります。
“働けない”のではなく、“働ける環境が用意されていない”だけかもしれない。
日本ではいまだに、「フルタイムで毎日出社できる人=戦力」という前提が残っていますが、ライフスタイルに制約のある人の力を活かせないのは、社会全体にとって大きな損失だと感じています。
数字が語る“見えない壁”
日本の男女格差について、「まだまだだよね」と漠然と思っている人は多いかもしれません。
でも実はその“まだまだ”は、世界的に見てもかなり深刻なレベルです。
たとえば、OECD(経済協力開発機構)加盟国の中で、日本の男女間の賃金格差はワーストレベル。
2023年のデータでは、日本の女性は男性に比べて平均で約22%も賃金が低いという結果が出ています。
さらに、企業の管理職に占める女性の割合も、わずか14%ほど。
他の先進国が30〜40%台であることを考えると、この数字は決して小さくありません。
なぜ差が生まれるのか?
それは“能力の差”ではなく、次のような構造的な“前提”が潜んでいます。
- 「男性が家計を支え、女性はサポート役」という古い価値観
- 長時間労働・年功序列・単身赴任など、ライフイベントと両立しにくい働き方の慣習
- そして、「ママになったらキャリアは諦めるもの」という無言の圧力
こうした古い前提が、女性のキャリア形成を難しくしているのです。
「働けない」のではなく、「働ける環境がない」だけかも
Re:mamaには、在宅かつ限られた時間の中でも、スキルと成果で活躍できる仕組みがあります。時間ではなく、「どんな価値を提供できるか」でつながる働き方。
会社のしくみに合わせて働くのではなく、その人のライフスタイルに合わせた働き方があれば、力を発揮できる女性はもっといるはず。
出産や介護を「マイナス」ではなく、「プラスの経験」として活かせる社会に変えていけたら――
それが、Re:mamaが目指す未来です。
Re:mamaがめざすのは“選択肢のある世界”
今は一歩踏み出せずにいる人も、「働ける環境さえあれば、まだやれるかも」と思えたなら、それはきっとあなたの中に“可能性の芽”がある証拠。そして私たちは、働き方の多様性を認めることが、女性のキャリアの可能性を広げる第一歩だと信じています。
賃金格差や管理職の壁をなくすために、今すぐすべてを変えることはできないかもしれません。
でも、「こういう働き方もアリだよね」と思える選択肢がひとつでも増えることが、その一歩になるはずです。
\ 在宅ワークをご希望のママ /
\ 委託を検討中の企業さま /